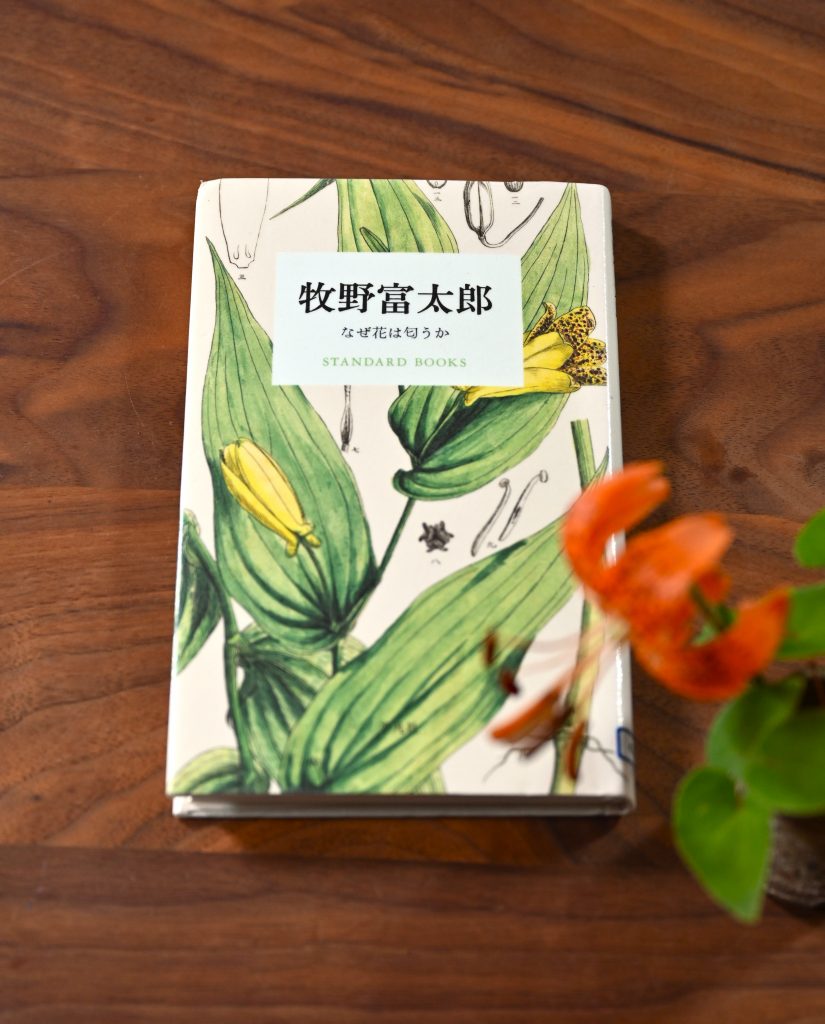今年はいつに無く暖かい冬ですね。とは言え軽井沢の冬は寒い。庭の手入れも畑仕事も無いこの季節は路面が凍結すると日中の散歩もままならない。この時期うってつけの仕事がこれ。
 編みかけのフード
編みかけのフード
ちくちくとひと針ひと針編む。今編んでいるフード、手が遅い私はここまでで3時間ほどかかる。編み物をしない方は「なんて面倒臭い事」と思うでしょうね。これ、やり始めると何故かやめられないのです。編んでいると無心になれると言うか心地よさすら感じる。同じ工程の繰り返しの単純作業とほんのわずかづつの成果が心に平安をもたらす。
竹細工、機織りや着物の仕立て。かつて日本人の暮らしの中には様々な手仕事があって暮らしを支えていた。生活を支える労働と言ってしまえばそれまでですが、手仕事にはそれ以外にも手元に意識を集中する事でほんのその時だけ日常を忘れたり、明日へのエネルギーを蓄えたりする効果もあるんですよね。ヨガや写経の世界観に通じるものを感じます。
 春夏ニット帽
春夏ニット帽
「芸は身を助く」我が家では母方に代々受け継がれてきた言葉。母からもらった毛糸を編みながら「なるほどこう言う意味もあったのか」と思うのです。
2023年の営業は12月10日を以て終了いたしました。来年は3月中旬に営業を開始する予定です。予定が決まりましたら本HPでお知らせいたします。
本年も余すこと半月、年末年始の気ぜわしい毎日かと思いますが、どうぞ皆様お健やかにお過ごしください。
 雲場池 2023年12月9日撮影
雲場池 2023年12月9日撮影
中古市場を探していると、時々胸踊る様な雑貨に出会ったりする。先日も、とある店の棚の奥にクリスマスに飾るスノードームみたいな可愛い卓上カレンダーを見つけた。よく見るとドームの海にシーソーに乗った2羽のペンギンと台座には日付を手動ダイヤルで設定できる様になっている。チープなお土産ですが私はこの手の雑貨に目がない。
 ペンギンドーム
ペンギンドーム
シーソーの台にはPHILLIP ISLANDの赤い文字。こう言う時にすごく便利なのがスマートフォンの検索機能だ。画面に現れたのは光あふれるペンギンの島。「フィリップアイランド」オーストラリアメルボルンから車で90分の所にある楽園。豊かな自然と野生動物が楽しめる。特に日没に見られるリトルペンギンのパレードが有名で多くの観光客が訪れる。広大な自然公園、海辺の遊歩道、多様な動植物、サーキットにワイナリー。行った事も無い島に思いをはせる。
中山道六十九次、江戸から数えて二十番目の宿場で北国街道との分岐点でもある追分宿(軽井沢町)。かつては中山道屈指の賑わいを誇る宿場であった。
 追分宿
追分宿
小田井宿から歩く事一里程、今の御代田駅の辺りから追分宿までは長い上り坂になる。追分宿は昔、旅人だけではなく地元の若い衆も遊びに来る者が多くこの坂道に差し掛かると、追分の宿から賑やかな声が聞こえて来て思わず笑顔になったと言われ、ついた名前が笑い坂。ちなみに「なつめクラフト」は笑い坂から佐久方面へ抜ける道沿いにあります。(笑い坂下)
 笑い坂
笑い坂
笑い坂を登り切った先が追分宿だ。
元禄時代は、わずか4.5キロの宿泊の中に本陣脇本陣の他に旅籠71軒、商店28軒、茶屋18軒を数え飯盛女が250人ほど居た。ここで歌われたのが追分節。全国に広がる馬子唄はここ追分から広まったと言われる。飯盛女達は銚子の袴でひづめの音を出しながら、旅人相手の酒席を大いに盛り上げた。 今ではあまり聞かれなくなった追分節だがあの頃は宿場中に響き渡っていた。
小諸出てみて 浅間の山にヨー 今朝も煙が 三筋立つ(中略)
七里八里の 恋路をふんでヨー 衣紋繕う 笑い坂
送りましょうか 送られましょか せめて枡形の 茶屋までも
(追分節歌詞から)
 追分節に謳われている 枡形の茶屋 津軽屋
追分節に謳われている 枡形の茶屋 津軽屋
 多肉植物
多肉植物
この花びらのような突起。植物と言うよりはマニュキアで綺麗に整えられた爪、カメレオンのトサカ、いや恐竜の角か。これら多肉植物と呼ばれているもの達は、葉や茎根に水を貯める南米などの乾燥地帯原産でサボテンの親戚らしい。
 モルタル造形の寄せ植え
モルタル造形の寄せ植え
アトリエ・ラ・シードさんの個展「モルタル造形と多肉展」に行って来ました。以前なつめクラフトにも、ドライフラワーや花の刺繍のヘアアクセサリーなど入れてもらっていた彼女の進化した現在の姿がこれ。数年前から多肉の魅力に取り憑かれているとは聞いていましたが、花の寄せ植えとは一味違う多肉植物の造形はまるで彫刻のようで美しい。お手製のモルタル鉢の寄せ植えはおとぎの世界へと誘いこむ。
 (奥から)メキシコプリドニス、エンジェルフィンガー、ダークアイス
(奥から)メキシコプリドニス、エンジェルフィンガー、ダークアイス
育て方はそれ程難しく無いようなので、いくつか購入。なつめ流に飾ってみました。アンティークグラスの紅い縁どり、年代物の小鉢、いつものコーヒーカップに浮かぶ偽りの花弁。うーむ、何やらニックネームを付けて呼びたくなってしまいたいくらい可愛い子達。
「あわゆき亭工房」と「アトリエ・ラ・シード」合同展は東御市にある土蔵ギャラリー胡桃倶楽部で10月6日~9日まで開催
長い、ながーい夏もやっと終わりが見えてきましたね。夏と言えば軽井沢ですが、実は「軽井沢が最も美しいのは秋」とも言われます。

軽井沢に多く自生しているツリバナの実が秋の気配を感じさせてくれます。

なつめクラフトも今年はちょっと遅めの模様替えです。手作りのマフラーやあったかニット帽で「森の街 軽井沢」を存分に散策してください。
8月も末と言うのに相変わらずの残暑。小諸市内の気温は午前10時で30度を超える。車を停めて風穴の深い森へと。昨晩降った雨で坂道は濡れムシムシとしたまとわり付く様な暑さだ。道の両脇には小さなほこらと石垣で囲われた室が点在していた。5号穴と書かれた木の扉を潜り入るなり夫と目を見合わせた。エアコンの最強を超える冷気が肌を刺す。更に石段を下る程にみるみる温度は下がり下室の気温計は4度を指していた。
 氷風穴全景
氷風穴全景
 第5号風穴入口
第5号風穴入口
氷風穴と呼ばれるこの場所はJR小諸駅から車で20分、小諸市氷地区にある。氷風穴の歴史は300年前江戸時代に遡る。池から天然氷を切り出し風穴で貯蔵して藩主へ献納していた。明治時代になると蚕の孵化のタイミングを人為的に調整し蚕糸業発展に大きな役割を担った。今も6基ほど残る氷風穴跡。第4号穴は今も使われていて農産物や花、漬物などの保存用に現在も稼働している。天然の冷蔵庫、電気代高騰の折使わない手はない。現在は第5号穴のみ見学用に公開されている。
 第5号風穴の室内
第5号風穴の室内
5号穴の石段を登り上の室に戻ると頭ほどの高さに一筋、細長い幻想的なもやがたなびいていた。ゆらゆらとまるで神の吐息ような霧雲は「風穴霧」と言うらしくそうはお目にかかれないしろもの。外気との温度差によって発生する風穴霧だが、あたかも現世と来世の境界線の様な。
 第5号穴に掛かる風穴霧
第5号穴に掛かる風穴霧
 御影用水温水路(正式名称は千ヶ滝湯川用水温水路)
御影用水温水路(正式名称は千ヶ滝湯川用水温水路)
軽井沢の西側、御代田町のほぼ境にある幅広の用水路。軽井沢にしては明るくどこかヨーロッパの様な風景が広がる。冷涼な軽井沢とは言え蒸し暑い日もたまにはある。水路からの風は涼を誘う。いつもはキラキラと輝く水面だが今朝は川霧が立ち込めていた。水辺に群れる鴨。これと言って目的のない日はここが良い。
 温水路 鴨
温水路 鴨
移住先を探してたまたま訪れた12年前、水路ぞいの小径を歩きながら、ふと「ここから続きの人生を始めたいな」そんな衝動にかられた。温水路を訪れたついでに店に寄ってくれたお客様は当時の私と似たような感想を語られる。
 温水路
温水路
この水路が出来たのは昭和42年。浅間山の水は冷たく稲作には不向きであった。この湧水の水温を上げて稲作の冷害を防ぐために作られたのがこの温水路。水深20センチ幅20メートル、太陽光を浴びゆったりとした流れは農業用水を超えて近隣の住民に癒しを与えてくれる思わぬ効果をもたらした。
用水ぞいの小径をときおり選んだ 夏の盛りの日もそこだけ涼しくって
松任谷由美1979年「悲しいほどお天気」の歌い出し、上水を用水に変えて‥

窓辺にかおる一輪の百合の花を、じっと抱きしめてやりたいような思いにかられても、百合の花は黙っています。そしてちっとも変わらぬ清楚な姿でただじっと匂っているのです。
牧野富太郎著書 「なぜ花は匂うか」より
 やまゆり 軽井沢・追分 7月25日撮影
やまゆり 軽井沢・追分 7月25日撮影
NHK連続テレビ小説らんまんの主人公牧野万太郎こと牧野富太郎の随筆を見つけた。土佐佐川町の造り酒屋に生まれ、幼い頃からただなんとなしに草木が好きであったと言う富太郎。
私は植物の愛人としてこの世に生まれてきたように感じます。(本文より)
 サクラソウ 軽井沢町の町花
サクラソウ 軽井沢町の町花
なぜ花は匂うのか。それは匂いで虫や鳥を呼び寄せ、受粉を手伝ってもらう為。と言ってしまえば簡単な事なのに、彼の随筆はそんな風には語られない。山野を教材に生涯採集と観察に明け暮れた、富太郎の知識は実に細やかでその言葉はとても優しい。
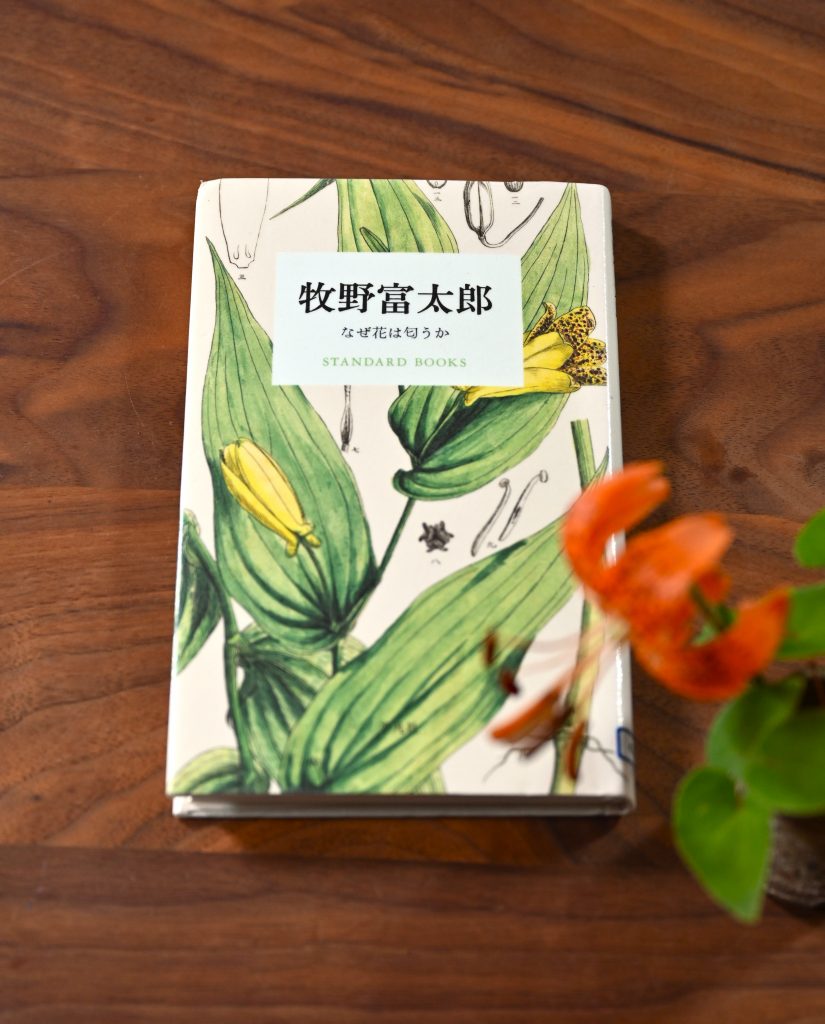
軽井沢追分にあるHandmade Work Shop Natsume Craftです